[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
Innerviewsにアップロードされたインタビューの翻訳です。
Allan Holdsworth
Harnessing momentum
by Anil Prasad
Copyright © 2008 Anil Prasad. All rights reserved.
Snakes and Laddersの創作課程を話してよ。
二つのグループはプレイの仕方が違うから、一方のグループ向けに選曲したら、その曲は別なグループには渡さ なかったんだ。概ね、それぞれのユニット向けに曲を書いたし。作曲のとっかかりは同じで、誰のための曲か? ということは無視するんだ。インプロヴァイズ しているうちにアイディアが浮かんだら、そのアイディアで作業を続けるんだ。何も起こらないこともあるけどね。たとえば、6年間の空白の間は(註1)全く創作意欲が沸かないし、音楽への関心も失せたんだ。人のライブにも行かなかったよ。長いこと、音楽には一切関わりたくなかったな。今ではまた作曲してるし、リハーサルする時間がなくてまだプレイしていない新曲も2、3あるんだ。このアルバムが片づいて次回作に取りかかるのが楽しみだよ。
作曲中にどうやってアイディアを記録するんだろう?
10年前は、イ ンプロヴァイズするとき録音しておいたんだ。レコーダーのスイッチを入れてからプレイする。おもしろいものが見つかったら聞き返して、「うん、これは形に なるな」なんて考えたんだ。[それに対して今では]一切録音しないって方法を採ることもあるよ。その時々の感情によるんだろうけど、曲の断片をメモしてお いて、体裁を整えられるようになるまで繰り返し確認するんだ。ホント速く仕上がることもあれば、数ヶ月かかることもあるな。Wardenclyffe Towerの“Sphere of Innocence”を例に取ろう。2時間で曲全体を書き上げたものの、途中にある転調の解決の仕方に満足してなかったんだ。99パーセントは1日もせずにできあがったのに対して、残り1パーセントに数ヶ月費やしたんだ。
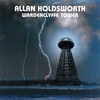
![]()
作曲には標準的な記譜[standard notation ](註2)を使うの?
いや、独自のシステムがあるんだ。意味はオレにしか分からない(笑)。インターバルの順列に基づいてるんだ。コードを考える場合は、コードを取り出す元となるスケールを見て、そのスケールだけを書くんだ。曲の出だしに使う特定のコードの場合、実際に指で押さえる場所を示す点を書き出すんだ。
慣習的な音楽[conventional music](註3)は読み書きするの?
いいや。
信じ難いね。
楽譜の読み方を学んだのは、父がしっかり読める腕のいいピアニストだったからなんだ。子供の頃にクラリネッ トを始めた当時は、父からはいつも読めって言われて、読んでいたよ。クラリネットをプレイしていた頃は、読むのは比較的簡単だと思ったよ。たいていの場 合、ある楽音が存在するのは一カ所[one place](註4)だ けだからね。ギターだと完全に混乱するんだ。同じ楽音をプレイできるポジションはたくさんあるから。[ギターの指板上の?]音の配列を覚えたばかりの頃、 父に何度か捕まって、問題を出されたんだ。オレは無茶苦茶なもんだから、父にはオレが読めないってバレたんだ。次第にわざわざ読まなくなってしまったん だ。
(註1)離婚でバタバタしていた期間。
(註2)恐らくは五線譜やコード譜、あるいはリード・シートを指すのだろう。
(註3)中身は(註2)と同じ。
(註4)管楽器における「運指」をplaceと数えるかどうかが判然としないため、不自然ながら直訳しておく。少なくとも日本語の感覚では、小中学生が、楽音に対応するリコーダーの押さえ方を「一カ所」と呼んだりはしない気がする。
……けど、だれだっていいじゃん、オイラなんか!
◎音楽関係のプロフィール
・ベース歴: 15年以上
・譜面の読み書き: 不自由
・初見演奏: 無理
・利用譜面エディタ: Allegro 2007→Finale 2010
・利用DTMソフト: Music Creator 2
※楽理関係を扱ったことを書いていますが、上記のように音楽については素人です。書かれている内容を鵜呑みにされないよう、ご注意ください。




