×
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
元々は東川誠一『旋法論 楽理の探究 』を読んでいたのだが
』を読んでいたのだが
ティンクトリスなどグレゴリオ聖歌の時代に通用していた
音楽理論を扱った本だということもあって
今日とは異なる階名の用法(「シ」がない)を前提に
議論が展開するとオイラには読めなくなってしまった
そこで、同じく東川『シャープとフラットのはなし―読譜法の今昔 』に手を出した
』に手を出した
冒頭の「序にかえて」は(それこそ古い階名が分からないと)
訳の分からない話で、実際その昔読もうとして挫折したのだが
(だから、現代の読者には「序にかえて」は序としてふさわしくないと思う)
『旋法論』を読むためにはやむなし、と覚悟を決めて(大げさだな)
その「序にかえて」を飛ばして読んでみると、これが実に面白い!
まだ読みかけながら、今日の慣習とは違うこともあるので
以下、備忘録として気になったところを記録しておく
ティンクトリスなどグレゴリオ聖歌の時代に通用していた
音楽理論を扱った本だということもあって
今日とは異なる階名の用法(「シ」がない)を前提に
議論が展開するとオイラには読めなくなってしまった
そこで、同じく東川『シャープとフラットのはなし―読譜法の今昔
冒頭の「序にかえて」は(それこそ古い階名が分からないと)
訳の分からない話で、実際その昔読もうとして挫折したのだが
(だから、現代の読者には「序にかえて」は序としてふさわしくないと思う)
『旋法論』を読むためにはやむなし、と覚悟を決めて(大げさだな)
その「序にかえて」を飛ばして読んでみると、これが実に面白い!
まだ読みかけながら、今日の慣習とは違うこともあるので
以下、備忘録として気になったところを記録しておく
ピアノを弾く方ならヘ音譜表とト音譜表を組み合わせた譜表を使うが
これにセンターCの線を加えた都合11本の線からなる譜表を
かつては当たり前のように使っていたようで、これを「ギャマット」という
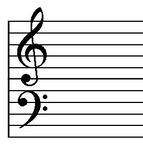
このギャマットから5本線を抜き出すことで、今日各パートが使う譜表になる
また、音部記号はギャマットから抜き出した5本線を読むための手がかりになるよう
どの線がどの音名を示すのかを示したものであること
グレゴリオ聖歌の時代だと音域が許せば抜き出す線が4本の場合もあったなどなど
五線譜にも面白い歴史があったことが記されている
これを踏まえて、「移調が難しい」という人は、「固定ド」ならぬ「固定ハ」
つまり、Cの位置する線を固定してでしか五線譜を読めないってのが
実は問題なのだから、今では使う機会が減ってしまった各種音部記号になじみ
どこがCでも譜表を読めるように訓練し、移調が必要になったら
適宜音部記号を自分で書き換え(書き換わったものと思い込んで)音符を読むと良いらしい
ただ、オイラはポピュラーでも一般的なヘ音譜表とト音譜表だけでもヒーヒー言うほど
まともに譜面を読めないので、移調なんて到底手出しできないんだけどね
ともかく、ピアノ向けの譜表は、むしろギャマットの名残、とでも考えるべき??
あと、ギャマットを前提にすると、線と線の間、それこそ「間(かん)」
いかにも文字を書き込みやすい「間」の一番下が、音名だとAに当たることも
譜表になじみのある人ならすぐ分かると思う
ここから上行で、間、線、間……と音名を読んでいけば
A B C D E F G……
となるわけだが、するとヘ音譜表の一番下に当たる間のAから
ト音譜表の一番上の間に当たるEまで、これがグレゴリオ聖歌の時代では
使い得る音域の全体だったようだ
その上で、ヘ音譜表のAよりも低い音、つまり一番下の線に該当する音が
既に限界を超えた低い音に当たるからか、素直に「G」とは表記せず
ギリシア文字に置き換えて「Γ」(ガンマ)と呼び、この「ガンマ」が由来で
センターCの線を追加した11本の譜表を「ギャマット」と呼ぶようになったようだ
今日だとオクターブ域はCから始まるものの、当時はAから始まって
(それこそ最初の間がAだから???)
書体を変えることでオクターブ域も区別していたようだ
仮に低いほうからオクターブ域を第1、第2……とすると
・第1: A~G
・第2: a~g
・第3: aa~ee
と表記したようで、第3にffやggがないのはギャマットに書き込める一番高い音
つまりト音譜表の一番上の間が「ee」だから、ということになるようだ
他方、上でも述べたように、かつての階名には「シ」がなかったこと
かつては「ド」ではなく「ウト」とされていたことなどから
階名唱には
ut, re, mi fa, sol, la
の6音を用いたようだ
で、この階名でutからlaまでに当たる音域を
ラテン語で「デドゥクツィオ」と言ったそうで
英語だとdeduction、だろうなぁ?
どーして音名だと7音なのに階名だと6音なのかは分からないけど
これはオクターブ域とはまったく別物、と考えなければならないようだ
ともかく、デドゥクツィオも低いほうから第1、第2……と数えると
当時はutと読める音が、ピッチクラスで言うとG C Fの三音しかなかった
これを踏まえて、ギャマットじゃなくて、今日慣れ親しんだヘ音譜表と
ト音譜表にデドゥクツィオをまとめると、こうなる
 このように、デドゥクツィオは区別されるものの
このように、デドゥクツィオは区別されるものの
中身は同じut …… laが繰り返されていることになる
この、階名で示される6音をやはりラテン語で「プロプリエタス」と言うそうで
英語だとpropertyと言うそうな
つまり、同一のプロプリエタスは、異なるデドゥクツィオに現れる
ということになるのかな??
デドゥクツィオは上にまとめたように
utがGのもの、Cのもの、Fのものと三種あることになり
この区別のポイントは2つある
1つ目はデドゥクツィオに音名のBがあるかどうか
ないもの、つまりutがCのものが「ナチュラル(本位)」なのだそうな
他方、デドゥクツィオに音名のBがあるもので
utがGの場合、Bの活字が当時は「b」の膨らんでいる部分が四角くなっていたそうで
「四角いb」と呼んだそうな
オクターブ域の区別と、パソコンで書ける活字の都合があるので
「□B」など、デドゥクツィオに応じてBを書き換えた上で「□」を添えることにする
同様にutがFのデドゥクツィオにあるBの活字は
「b」の膨らみを極端に丸くしたそうで、「丸いb」と呼んだそうな
こちらは「□」の代わりに「○」を添えて書いておく
この、活字の書き分けに由来するんだと思うが
ここからutがGのデドゥクツィオを「硬いb」
Fのデドゥクツィオを「柔らかいb」と呼んだようなのだが
上記のように本来は音名Bを区別す「四角い」「丸い」が由来
これが表現を変えてデドゥクツィオの区別と混同されてしまったようで
ティントクリスは「しっかり区別しろ」と教則本で強調していたそうな
こうしたBの区別が今日使われている臨時記号や変化記号の起源のようだ
ともかくここから
当時の音楽教育ではギャマットにおいて
どの線、どの間に、どの音名が来て、その音名がどう階名唱され得るか?
これを丸暗記することが一番最初にやるべきことだったようだ
これを今日なじみのあるピアノ向けの譜表に整理すると
こうなるだろう
 音名Bを「mi」や「fa」と階名唱する場合はについて
音名Bを「mi」や「fa」と階名唱する場合はについて
デディクツィオのutがGか、Fかによって
Bが四角いか、丸いかも代わってくるため、その別を
階名の前に添えるのが慣習だったようだ
さて、それこそ教会旋法に基づくグレゴリオ聖歌などでは
今日のように広い音域を使わなかったようだが
それでも超えることもなくはなかったことから
デディクツィオを超えた音を用いる際の階名唱について
どうするべきか? という問題が出てくる
一応規則としては
・元のデディクツィオに極力留まりつつ
・移った先のデディクツィオではutを使わない
となるようで、ヘ音譜表でΓをutと歌って上行を続け
Fに至った際の階名はどうなるか? を例にとると
手前のEをlaと歌った段階で
1つ上のデディクツィオに移ることを合図するように
即座にmiと読み替える、つまり
Eのピッチで短くlaと歌ってから即座にmiと歌いなおして
Fはfaと歌うことになる、というわけだ
ただ、んなこといえば
Cの段階でfaをutと読み替えてもいいのではないか?
ということになるわけだが、
・元のデディクツィオに極力留まりつつ
という規則が効いてくるので
ギリギリまで元のデディクツィオのま階名を維持することになる
今の例だとEがその限界に当たって、こいつが今日の用語で言う
ピボット・ノート、ということになるんだろうなぁ??
この、デディクツィオの移動に伴う階名読み替えを
ラテン語で「ムタツィオ」というそうで
英語だとmutationってことになるそうな
当時の階名についてこのくらい押さえておけば
『旋法論』は読めるのかなぁ?
とはいえ、『シャープとフラットのはなし』自体がとても面白いので
このまま最後まで読むことにしよう
これにセンターCの線を加えた都合11本の線からなる譜表を
かつては当たり前のように使っていたようで、これを「ギャマット」という
このギャマットから5本線を抜き出すことで、今日各パートが使う譜表になる
また、音部記号はギャマットから抜き出した5本線を読むための手がかりになるよう
どの線がどの音名を示すのかを示したものであること
グレゴリオ聖歌の時代だと音域が許せば抜き出す線が4本の場合もあったなどなど
五線譜にも面白い歴史があったことが記されている
これを踏まえて、「移調が難しい」という人は、「固定ド」ならぬ「固定ハ」
つまり、Cの位置する線を固定してでしか五線譜を読めないってのが
実は問題なのだから、今では使う機会が減ってしまった各種音部記号になじみ
どこがCでも譜表を読めるように訓練し、移調が必要になったら
適宜音部記号を自分で書き換え(書き換わったものと思い込んで)音符を読むと良いらしい
ただ、オイラはポピュラーでも一般的なヘ音譜表とト音譜表だけでもヒーヒー言うほど
まともに譜面を読めないので、移調なんて到底手出しできないんだけどね
ともかく、ピアノ向けの譜表は、むしろギャマットの名残、とでも考えるべき??
あと、ギャマットを前提にすると、線と線の間、それこそ「間(かん)」
いかにも文字を書き込みやすい「間」の一番下が、音名だとAに当たることも
譜表になじみのある人ならすぐ分かると思う
ここから上行で、間、線、間……と音名を読んでいけば
A B C D E F G……
となるわけだが、するとヘ音譜表の一番下に当たる間のAから
ト音譜表の一番上の間に当たるEまで、これがグレゴリオ聖歌の時代では
使い得る音域の全体だったようだ
その上で、ヘ音譜表のAよりも低い音、つまり一番下の線に該当する音が
既に限界を超えた低い音に当たるからか、素直に「G」とは表記せず
ギリシア文字に置き換えて「Γ」(ガンマ)と呼び、この「ガンマ」が由来で
センターCの線を追加した11本の譜表を「ギャマット」と呼ぶようになったようだ
今日だとオクターブ域はCから始まるものの、当時はAから始まって
(それこそ最初の間がAだから???)
書体を変えることでオクターブ域も区別していたようだ
仮に低いほうからオクターブ域を第1、第2……とすると
・第1: A~G
・第2: a~g
・第3: aa~ee
と表記したようで、第3にffやggがないのはギャマットに書き込める一番高い音
つまりト音譜表の一番上の間が「ee」だから、ということになるようだ
他方、上でも述べたように、かつての階名には「シ」がなかったこと
かつては「ド」ではなく「ウト」とされていたことなどから
階名唱には
ut, re, mi fa, sol, la
の6音を用いたようだ
で、この階名でutからlaまでに当たる音域を
ラテン語で「デドゥクツィオ」と言ったそうで
英語だとdeduction、だろうなぁ?
どーして音名だと7音なのに階名だと6音なのかは分からないけど
これはオクターブ域とはまったく別物、と考えなければならないようだ
ともかく、デドゥクツィオも低いほうから第1、第2……と数えると
当時はutと読める音が、ピッチクラスで言うとG C Fの三音しかなかった
これを踏まえて、ギャマットじゃなくて、今日慣れ親しんだヘ音譜表と
ト音譜表にデドゥクツィオをまとめると、こうなる
中身は同じut …… laが繰り返されていることになる
この、階名で示される6音をやはりラテン語で「プロプリエタス」と言うそうで
英語だとpropertyと言うそうな
つまり、同一のプロプリエタスは、異なるデドゥクツィオに現れる
ということになるのかな??
デドゥクツィオは上にまとめたように
utがGのもの、Cのもの、Fのものと三種あることになり
この区別のポイントは2つある
1つ目はデドゥクツィオに音名のBがあるかどうか
ないもの、つまりutがCのものが「ナチュラル(本位)」なのだそうな
他方、デドゥクツィオに音名のBがあるもので
utがGの場合、Bの活字が当時は「b」の膨らんでいる部分が四角くなっていたそうで
「四角いb」と呼んだそうな
オクターブ域の区別と、パソコンで書ける活字の都合があるので
「□B」など、デドゥクツィオに応じてBを書き換えた上で「□」を添えることにする
同様にutがFのデドゥクツィオにあるBの活字は
「b」の膨らみを極端に丸くしたそうで、「丸いb」と呼んだそうな
こちらは「□」の代わりに「○」を添えて書いておく
この、活字の書き分けに由来するんだと思うが
ここからutがGのデドゥクツィオを「硬いb」
Fのデドゥクツィオを「柔らかいb」と呼んだようなのだが
上記のように本来は音名Bを区別す「四角い」「丸い」が由来
これが表現を変えてデドゥクツィオの区別と混同されてしまったようで
ティントクリスは「しっかり区別しろ」と教則本で強調していたそうな
こうしたBの区別が今日使われている臨時記号や変化記号の起源のようだ
ともかくここから
当時の音楽教育ではギャマットにおいて
どの線、どの間に、どの音名が来て、その音名がどう階名唱され得るか?
これを丸暗記することが一番最初にやるべきことだったようだ
これを今日なじみのあるピアノ向けの譜表に整理すると
こうなるだろう
デディクツィオのutがGか、Fかによって
Bが四角いか、丸いかも代わってくるため、その別を
階名の前に添えるのが慣習だったようだ
さて、それこそ教会旋法に基づくグレゴリオ聖歌などでは
今日のように広い音域を使わなかったようだが
それでも超えることもなくはなかったことから
デディクツィオを超えた音を用いる際の階名唱について
どうするべきか? という問題が出てくる
一応規則としては
・元のデディクツィオに極力留まりつつ
・移った先のデディクツィオではutを使わない
となるようで、ヘ音譜表でΓをutと歌って上行を続け
Fに至った際の階名はどうなるか? を例にとると
手前のEをlaと歌った段階で
1つ上のデディクツィオに移ることを合図するように
即座にmiと読み替える、つまり
Eのピッチで短くlaと歌ってから即座にmiと歌いなおして
Fはfaと歌うことになる、というわけだ
ただ、んなこといえば
Cの段階でfaをutと読み替えてもいいのではないか?
ということになるわけだが、
・元のデディクツィオに極力留まりつつ
という規則が効いてくるので
ギリギリまで元のデディクツィオのま階名を維持することになる
今の例だとEがその限界に当たって、こいつが今日の用語で言う
ピボット・ノート、ということになるんだろうなぁ??
この、デディクツィオの移動に伴う階名読み替えを
ラテン語で「ムタツィオ」というそうで
英語だとmutationってことになるそうな
当時の階名についてこのくらい押さえておけば
『旋法論』は読めるのかなぁ?
とはいえ、『シャープとフラットのはなし』自体がとても面白いので
このまま最後まで読むことにしよう
PR
COMMENT
HN:
べぇす
性別:
男性
趣味:
音楽(素人レベル)
自己紹介:
一応趣味でベースを弾く。
……けど、だれだっていいじゃん、オイラなんか!
◎音楽関係のプロフィール
・ベース歴: 15年以上
・譜面の読み書き: 不自由
・初見演奏: 無理
・利用譜面エディタ: Allegro 2007→Finale 2010
・利用DTMソフト: Music Creator 2
※楽理関係を扱ったことを書いていますが、上記のように音楽については素人です。書かれている内容を鵜呑みにされないよう、ご注意ください。
……けど、だれだっていいじゃん、オイラなんか!
◎音楽関係のプロフィール
・ベース歴: 15年以上
・譜面の読み書き: 不自由
・初見演奏: 無理
・利用譜面エディタ: Allegro 2007→Finale 2010
・利用DTMソフト: Music Creator 2
※楽理関係を扱ったことを書いていますが、上記のように音楽については素人です。書かれている内容を鵜呑みにされないよう、ご注意ください。
忍者解析
クリック募金
Amazon.co.jp
最新記事
(03/12)
(03/07)
(03/07)
(01/27)
(01/25)
ブログ内検索
最新TB
画像を食べちゃうひつじパーツ




